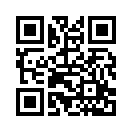2015年08月17日
R1200GSその2
こんばんは。えがすらです。
筋トレを続けてるんですが、カーチャンに
「厚みが増してきた!横も奥行きもでかくなってどうする!!」
と怒られてます。
どうしろというのだ・・・
さて、R1200GS二回目です。
完全に文章を下書き無しで書いているので、論点がとっちらかって、ひどいことになってます。
まあ、テキトーに今日も書き散らかしますけど。
前回で機能的なことを書いたので、今日は年式の違いを書いてみようかと思います。
その1で書いた通り、
R1200GSは2004年にデビューしています。
初期型はこんな感じ。

2004~2007までがこの型です。
特徴としては
・タンクの横が樹脂。色は黒が多いけど、カラーによってはシルバーだったり。
・顔が後の型とは違う。
・電子制御(トラクションコントロール)がない。
などがあります。
初期型で注意するのはブレーキです。
BMWのバイクは2003年ごろから「サーボブレーキ」なるものを装備しています。
こいつが厄介なんです。
中身としては、ブレーキをかける力をモーターでアシストする、というもの。
なので、ちょっとの力でハードブレーキングが可能です。ABSも付いているので
握りゴケも怖くないよ!的なうたい文句だったようですが・・・
このアシストがバイクの電源が入っていないと作動しません。
つまりは、キーのオンオフによってブレーキのタッチが変わります。
モーターのアシストがない状態でもガン握りすれば、効くんですけど
ものすごい効きにくい。
モーターのアシストがあれば、人差し指一本でブレーキかけてもカツーン!!と効いてくれます。
・・・・はっきりいって使いにくい。
更に言えば、この「サーボブレーキ」
よく壊れます。
しかも車両の保障期間が終わったくらいによく壊れます。
修理にはうん十万かかるという鬼畜っぷり。
R1200GSが欲しい!っていう人はブレーキの仕様だけはよーーーく確認しましょう。
ちなみにBMWもこれはしくじったと思ったのか、2007年よりサーボブレーキは廃止されます。
初期型の見た目が好きな人は2007年を狙いましょう。
次の型で見た目が変わります。

これは2008~2009年までの型です。
R1200GS TU とか言われます。
TUが何の略か忘れた。テクニカルなんとかだったとおもうけども・・・
それはさておき、この型の特徴です。
・ASC(オートマチックスタビリティコントロール)が搭載
・タンクの横にアルミのカバーがついた
・なんかあちこち現代的にリファイン
・ESA搭載!
こんな特徴があります。
この型まではエンジンがSOHCを採用しています。
国産バイクからすると、SOHCwwwプゲラwwwwって感じになりますが
意外といいものなんです。SOHC。
アクセル開けても反応がいい感じに鈍いんです。
ここら辺の話はあとから書きます。
そして、ESAです。
ESAとはエレクトリックサスペンションなんちゃらの略です。また忘れた。
具体的にどんな機能かと言えば、
サスペンションのダンパー性能を手元のスイッチで任意に設定できます。
たとえば今日は二人乗り、街乗り主体。
ならば、ESAを二人乗りでやわらかい設定にする。
今日は一人でワインディングを走る高速ツーリング、それならば一人乗りでハードなサスセッティング
こんな感じで設定できるわけです。
何がよいって、走りながら設定の変更が可能なんです。
コレ、意外と走りが変わります。
試す機会があるなら、是非お試しください。
そして、2010年以降の型がこんな感じになります。

見た目は全然変わりませんねw
2010年以降の型は所謂「空冷最終モデル」と言われます。
何が違うかといえば、エンジンがDOHC化されます。
ダブルオーバーヘッドカムシャフトですよ!奥さん!
水冷で四気筒で20000回転まで回るぜ!とか言ってたCBR250Rのときと比べると
やたらと古臭く感じますよねw
でも、これがBMWのこだわりだったんです。
ちなみに、SOHCとDOHCの見分け方はシリンダーヘッドにある黒いカバーです。
横から出てたらSOHC、下から出てたらDOHCです。
GSだけじゃなくて、RTやRについても同じことが言えるので覚えておきましょー。
既にコレだけで相当長いですけど、それぞれ乗った感想を書き散らかしてみます。
基本的にR1200GSそれそのものはオールラウンダーです。
バイクっていうものは、それぞれのジャンルで特化して作られてるものが多いです。
たとえば、スーパーカブを配達に使えば最高ですが、高速道路を走れば最低の性能を発揮します。
CBR1000RRでサーキットを攻めれば最高ですが、郵便配達したら最悪のウンコマシンです。
得意不得意がはっきりしているのが通常ですが、R1200GSは違います。
さすがに郵便配達には不向きですが、オンもオフも高速道路も街乗りも、けっこう器用にこなします。
これが通常のバイク趣味の人が「バイクでする楽しみ」をほとんどカバーしてくれてるんです。
乗りやすさのおかげで峠を攻めても速い。SSをカモるR1200GSはたくさん知ってます。
ライディングポジションはオフロードバイクらしく、すごく楽。
背筋が伸び、腕も自然にハンドルへ届きます。
しっかりとしたコシのあるシートでケツへのダメージも少ない。
BMWのウインドプロテクションには定評がありますが、R1200GSもしっかりしています。
走りながらジッポに火つけれるくらい風から守ってくれます。
その1で書いたテレレバー、パラレバーのおかげで、走行中の身体の影響は少ないです。
これはタンデム走行時にも超有効に働きます。
テレレバー、パラレバー搭載のバイクでのタンデムは、タンデマーがガッチリ寝てしまうことが悩みになります。
それくらい安定してる。
これまで書いた各年式ごとの違いですが
いちばんの変化は、やはり電子制御とエンジンの違いでしょう。
ESAやトラクションコントロールの差は確実に出ます。
特に途中から導入されたASCはワインディングで効果絶大です。
立ち上がりでガバ開けしても、リアが滑らない。
安心してラフにアクセル操作が出来ます。
SOHC、DOHCについては実は好みが出ます。
DOHC化された後のR1200GSは低速トルクが増したこと、スムーズに回転数が上がること
この二つが体感できる変化です。
空冷の二気筒のくせに、バンバン回ってくれます。ちゃんと空冷らしさを残しつつ
絶妙な感じです。
でも、僕はSOHCの大雑把で妙に味のある回り方が好きだったりします。
アクセル操作に対してもやっぱり、どこか大雑把に返答をしてくれる。
好きなんです。そういうおおらかなところが。
お金があったら、一度は手元におきたいバイクだなあとか思います。
筋トレを続けてるんですが、カーチャンに
「厚みが増してきた!横も奥行きもでかくなってどうする!!」
と怒られてます。
どうしろというのだ・・・
さて、R1200GS二回目です。
完全に文章を下書き無しで書いているので、論点がとっちらかって、ひどいことになってます。
まあ、テキトーに今日も書き散らかしますけど。
前回で機能的なことを書いたので、今日は年式の違いを書いてみようかと思います。
その1で書いた通り、
R1200GSは2004年にデビューしています。
初期型はこんな感じ。

2004~2007までがこの型です。
特徴としては
・タンクの横が樹脂。色は黒が多いけど、カラーによってはシルバーだったり。
・顔が後の型とは違う。
・電子制御(トラクションコントロール)がない。
などがあります。
初期型で注意するのはブレーキです。
BMWのバイクは2003年ごろから「サーボブレーキ」なるものを装備しています。
こいつが厄介なんです。
中身としては、ブレーキをかける力をモーターでアシストする、というもの。
なので、ちょっとの力でハードブレーキングが可能です。ABSも付いているので
握りゴケも怖くないよ!的なうたい文句だったようですが・・・
このアシストがバイクの電源が入っていないと作動しません。
つまりは、キーのオンオフによってブレーキのタッチが変わります。
モーターのアシストがない状態でもガン握りすれば、効くんですけど
ものすごい効きにくい。
モーターのアシストがあれば、人差し指一本でブレーキかけてもカツーン!!と効いてくれます。
・・・・はっきりいって使いにくい。
更に言えば、この「サーボブレーキ」
よく壊れます。
しかも車両の保障期間が終わったくらいによく壊れます。
修理にはうん十万かかるという鬼畜っぷり。
R1200GSが欲しい!っていう人はブレーキの仕様だけはよーーーく確認しましょう。
ちなみにBMWもこれはしくじったと思ったのか、2007年よりサーボブレーキは廃止されます。
初期型の見た目が好きな人は2007年を狙いましょう。
次の型で見た目が変わります。

これは2008~2009年までの型です。
R1200GS TU とか言われます。
TUが何の略か忘れた。テクニカルなんとかだったとおもうけども・・・
それはさておき、この型の特徴です。
・ASC(オートマチックスタビリティコントロール)が搭載
・タンクの横にアルミのカバーがついた
・なんかあちこち現代的にリファイン
・ESA搭載!
こんな特徴があります。
この型まではエンジンがSOHCを採用しています。
国産バイクからすると、SOHCwwwプゲラwwwwって感じになりますが
意外といいものなんです。SOHC。
アクセル開けても反応がいい感じに鈍いんです。
ここら辺の話はあとから書きます。
そして、ESAです。
ESAとはエレクトリックサスペンションなんちゃらの略です。また忘れた。
具体的にどんな機能かと言えば、
サスペンションのダンパー性能を手元のスイッチで任意に設定できます。
たとえば今日は二人乗り、街乗り主体。
ならば、ESAを二人乗りでやわらかい設定にする。
今日は一人でワインディングを走る高速ツーリング、それならば一人乗りでハードなサスセッティング
こんな感じで設定できるわけです。
何がよいって、走りながら設定の変更が可能なんです。
コレ、意外と走りが変わります。
試す機会があるなら、是非お試しください。
そして、2010年以降の型がこんな感じになります。

見た目は全然変わりませんねw
2010年以降の型は所謂「空冷最終モデル」と言われます。
何が違うかといえば、エンジンがDOHC化されます。
ダブルオーバーヘッドカムシャフトですよ!奥さん!
水冷で四気筒で20000回転まで回るぜ!とか言ってたCBR250Rのときと比べると
やたらと古臭く感じますよねw
でも、これがBMWのこだわりだったんです。
ちなみに、SOHCとDOHCの見分け方はシリンダーヘッドにある黒いカバーです。
横から出てたらSOHC、下から出てたらDOHCです。
GSだけじゃなくて、RTやRについても同じことが言えるので覚えておきましょー。
既にコレだけで相当長いですけど、それぞれ乗った感想を書き散らかしてみます。
基本的にR1200GSそれそのものはオールラウンダーです。
バイクっていうものは、それぞれのジャンルで特化して作られてるものが多いです。
たとえば、スーパーカブを配達に使えば最高ですが、高速道路を走れば最低の性能を発揮します。
CBR1000RRでサーキットを攻めれば最高ですが、郵便配達したら最悪のウンコマシンです。
得意不得意がはっきりしているのが通常ですが、R1200GSは違います。
さすがに郵便配達には不向きですが、オンもオフも高速道路も街乗りも、けっこう器用にこなします。
これが通常のバイク趣味の人が「バイクでする楽しみ」をほとんどカバーしてくれてるんです。
乗りやすさのおかげで峠を攻めても速い。SSをカモるR1200GSはたくさん知ってます。
ライディングポジションはオフロードバイクらしく、すごく楽。
背筋が伸び、腕も自然にハンドルへ届きます。
しっかりとしたコシのあるシートでケツへのダメージも少ない。
BMWのウインドプロテクションには定評がありますが、R1200GSもしっかりしています。
走りながらジッポに火つけれるくらい風から守ってくれます。
その1で書いたテレレバー、パラレバーのおかげで、走行中の身体の影響は少ないです。
これはタンデム走行時にも超有効に働きます。
テレレバー、パラレバー搭載のバイクでのタンデムは、タンデマーがガッチリ寝てしまうことが悩みになります。
それくらい安定してる。
これまで書いた各年式ごとの違いですが
いちばんの変化は、やはり電子制御とエンジンの違いでしょう。
ESAやトラクションコントロールの差は確実に出ます。
特に途中から導入されたASCはワインディングで効果絶大です。
立ち上がりでガバ開けしても、リアが滑らない。
安心してラフにアクセル操作が出来ます。
SOHC、DOHCについては実は好みが出ます。
DOHC化された後のR1200GSは低速トルクが増したこと、スムーズに回転数が上がること
この二つが体感できる変化です。
空冷の二気筒のくせに、バンバン回ってくれます。ちゃんと空冷らしさを残しつつ
絶妙な感じです。
でも、僕はSOHCの大雑把で妙に味のある回り方が好きだったりします。
アクセル操作に対してもやっぱり、どこか大雑把に返答をしてくれる。
好きなんです。そういうおおらかなところが。
お金があったら、一度は手元におきたいバイクだなあとか思います。